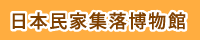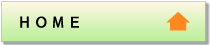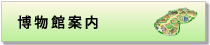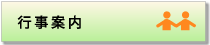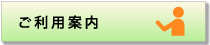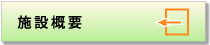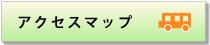![]()
― 2012年度 ―
2012年4月掲載 (桜だより 4月7日現在)
 |
 |
| 「布施の長屋門」。入ったところ、八分咲きのソメイヨシノ | 枝垂れ桜が麦の穂ときれいに調和しています |
 |
 |
| 「日向椎葉の民家」と桜が絵になります | 「大和十津川の民家」前の桜も見事です |
2012年4月掲載 その1
 |
 |
| ハナズオウ(花蘇芳) | ドウダンツツジ(灯台躑躅) |
| マメ科の植物で、葉に先だち枝に直接花をつけます。 | 別名「満天星」、白い小さな花が沢山咲きます。 |
 |
 |
| ライラック(紫丁香花) | キクモモ(菊桃) |
| 和名「むらさきはしどい」、リラとも呼ばれ香水の原料になります。 | 江戸時代からある品種で、菊のような花をつけることで、この名前になりました。 |
 |
 |
| カンサイタンポポ(関西蒲公英) | シャガ(著莪) |
| 長野以西に分布する和タンポポ、館内に沢山咲いています。 | 木陰の湿った場所に群生する植物で、アヤメに似た白い花をつけます。 |
2012年4月掲載 その2
 |
 |
| ヤエヤマブキ(八重山吹) | シラン(紫蘭) |
| 和歌にも詠まれた山吹が「大和十津川の民家」横で咲いています。 | 湿地に群生するラン科の花です。「信濃秋山の民家」近くで咲いています。 |
 |
 |
| ツツジ(躑躅) | ボタン(牡丹) |
| 日本では108種も分布する花です。画像の品種は「オオムラサキ」です。 | 中国原産で日本には奈良時代に渡来しました。「名取草」「深見草」とも呼ばれています。 |
2012年4月掲載 その3
 |
 |
| ヤグルマギク(矢車菊) | コデマリ(小手毬) |
| ヨーロッパ原産、江戸時代に渡来しました。花が「矢車」に似ているので、この名前になりました。 | 中国原産、白い小花を集団で咲かせ、小さな手まりに見えることからこの名前になりました。 |
 |
 |
| ヒメシャリンバイ(姫車輪梅) | ヒメジョオン(姫女苑) |
| バラ科の常緑低木、枝先に花が車輪のように咲くので、この名前になりました。 | 北アメリカ原産、キク科の植物で明治時代に渡来しました。鉄道と共に広まったことから「鉄道草」とも呼ばれます。 |
 |
 |
| アヤメ(菖蒲) | シロツツジ(白躑躅) |
| 五月を象徴する花です。「北河内の茶室」周辺に沢山咲きました。 | 館内には沢山のツツジが咲いています。その中でも「白琉球」という白ツツジが「越前敦賀の民家」横で見事に咲いています。 |
2012年5月掲載 その1
 |
 |
| ヤリズイセン(槍水仙) | キショウブ(黄菖蒲) |
| 南アフリカ原産アヤメ科の花、「河内布施の長屋門」入り口にある花壇で咲きました。 | 水辺に群生するアヤメ科の多年草、梅林横の池周辺に咲いています。 |
 |
 |
| ムラサキツユクサ(紫露草) | シャクヤク(芍薬) |
| 北米原産、明治時代初めに渡来。朝に花が開き、午後には萎みます。 | 中国原産、花は牡丹に似ていますが、牡丹が咲き終わるのを待つようにして、咲き出しました。 |
2012年5月掲載 その2
 |
 |
| ニワゼキショウ(庭石菖) | アザミ(薊) |
| 明治時代中期に帰化したアヤメ科の植物。白や薄紫色の可愛い花です。 | 別名「刺草」、美しい紫色の花を咲かせますが、葉は厚く鋸状のトゲがあります。 |
 |
 |
| バイカウツギ | 梅の実 |
| 名前の通り、梅に似た白い花ですが、アジサイ科の植物です。「布施長屋門」入り口に咲いています。 | 梅林の梅の実が、大きくなってきました。収穫時期は6月から7月の間です。 |
2012年6月掲載
 |
 |
| アジサイ(紫陽花) | エラブユリ(永良部百合) |
| 館内にはいろいろな種類のアジサイが咲いています。(画像はガクアジサイの一種)。 | 「奄美の高倉」前に、今年も白くうつくしいユリが咲きはじめました。 |
 |
 |
| ルリヤナギ(瑠璃柳) | ホタルブクロ(蛍袋) |
| 「飛騨白川の民家」裏に咲いています。葉が柳に似ているので、この名前になりました。 | 昔、子どもたちが蛍をこの花に入れて遊んだことから、この名前になったと伝えられています。 梅雨時期に花をつけるので、別名「雨降り花」とも言われます。 |
2012年7月掲載
 |
 |
| オニユリ (鬼百合) | ゴマ (胡麻) |
| 花の色や形から「赤鬼」を連想させることから、この名前になりました。 | お茶とともに古くから庶民に親しまれ、食用にされています。7月から8月に花が咲き、9月に実ができます。 |
 |
 |
| キスゲ(黄菅) | ヒメオウギズイセン(姫扇水仙) |
| 鮮やかな淡黄色のユリに似た花が館内に咲いています。 | 盆花としても知られる花ですが、明治時代にヨーロッパから渡来した花です。 |
 |
 |
| キキョウ(桔梗) | ソバ(蕎麦) |
| 秋の七草の一つですが、「摂津能勢の民家」横の花壇に、一足早く咲きました。 | 雨の少ない乾燥した荒地でも育つ、強い植物です。 |
2012年8月掲載
 |
 |
| バナナ | 綿の花 |
| 開花は一本の茎に1回のみで、開花後は吸芽を残し、根元から枯れてしまいます。 | 開花1日目は白く、2日目以降はピンク色になります。「日向椎葉の民家」前に咲いています。 |
 |
 |
| ソバの花 (蕎麦) | ノウゼンカズラ (凌霄花) |
| 食用として古くから民家に栽培されていました。「日向椎葉の民家」前に咲いています。 | 中国原産で、平安時代に渡来しました。「奄美の高倉」横に咲いています。 |
2012年9月掲載
 |
 |
| サルスベリ (百日紅) | フヨウ (芙蓉) |
| すべすべした樹皮で、猿もすべる木から「猿滑」と表記されることもあります。 | 朝咲いて、夕方萎む1日花。「南部の曲家」前に咲いています。 |
 |
 |
| タマスダレ (玉簾) | コスモス (秋桜) |
| ヒガンバナ科の球根、一本の花茎に一つだけ花が咲きます。 | 秋の季節を象徴する花です。「飛騨白川の民家」横などに咲いています。 |
 |
 |
| キバナコスモス (黄花秋桜) | ニラ (韮) |
| メキシコ原産で、ヨーロッパ経由で大正時代に渡来しました。 | 花は清楚ですが、独特な臭いがします。館内の畑で咲いています。 |
2012年10月掲載
 |
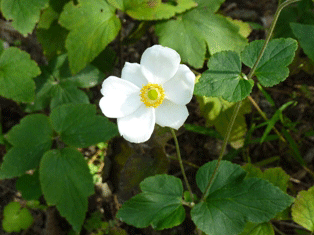 |
| ムラサキカタバミ ( 紫酢漿草 ) | シュウメイギク ( 秋明菊 ) |
| ブラジル原産の帰化植物。葉はクローバーにそっくりです。 | キクと名がついていますが、アネモネの仲間です。 「貴船菊」とも言われます。 |
 |
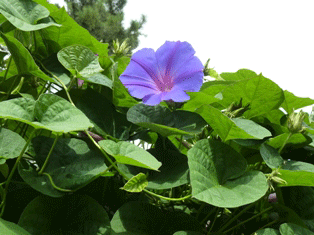 |
| ユウゼンギク ( 友禅菊 ) | セイヨウアサガオ ( 西洋朝顔 ) |
| 北アメリカ原産で、日本には明治時代に渡来しました。 荒地や路傍に咲く強い花です。 |
夏から秋にかけて、きれいな濃い青色の花を咲かせます。 |
2012年11月掲載
 |
 |
| ツワブキ (石蕗) | キンミズヒキ (金水引) |
| キク科の多年草、昔から庭の下草として植えられました。葉は解毒効果があり、薬草として用いました。 | バラ科の多年草、薬草として、止血や下痢止めに用いました。 |
 |
 |
| イロハモミジ (いろは紅葉) | チェリーセージ |
| 「飛騨白川の民家」近くのモミジが紅葉してきました。 | シソ科の植物で、目の覚める赤色の花を、春から秋 休みなく咲かせます。 |
2012年11月掲載 その2
 |
 |
| フイリススキ (斑入り薄) | サザンカ (山茶花) |
| 後方の紅葉したハゼとのコントラストが美しいススキです。 | 童謡「たきび」に登場する寒い時期の代表花です。 |
 |
 |
| ノコンギク (野紺菊) | ドウダンツツジ (灯台躑躅) |
| 寄せ植えした野生のコンギク、紫色のかわいい花です。 | 鮮やかな赤色の葉が目を惹きます。 |
2013年 1月掲載
 |
 |
| ハナユズ (花柚子) | ロウバイ (蝋梅) |
| 「一才柚子」とも呼ばれ、柚子より低木です。名前の通り、花にも香りがあります。 | 唐の国から日本に来たので、「唐梅」とも呼ばれ、花びらが蝋のような色をしているので、この名前になりました。良い香りがします。 |
 |
 |
| ニホンスイセン (日本水仙) | サザンカ (山茶花) |
| 「雪中花」とも呼ばれ、早いものは12月頃から咲き始めます。「奄美大島の高倉」前の水仙畑に花を付け始めました。 | 野生の花色は桃色を交えた白色ですが、品種改良により、赤やピンクなどの花を付けます。 |
2013年 2月10日掲載
| 梅林には、約80本の梅の木が植えられています。その中で早咲きの梅が、3分咲きになってきました。 | |
 |
 |
 |
 |
2013年 2月17日掲載
| 梅林全体では3分咲きですが、開花の早い木は5分まで咲いています。 | |
 |
 |
 |
 |
2013年 2月24日掲載
| 寒い日が続き、梅の開花も遅れ気味ですが、ようやく六分咲きまできています。 | |
 |
 |
 |
 |
2013年 3月 3日掲載
| 梅林が七分咲きとなり、写真撮影や観賞される方が増えています。 | |
 |
 |
 |
 |
2013年 3月 9日掲載
| 梅林がほぼ満開になりました。そして、修復された「堺の風車」と梅林の風景が戻ってきました。 | |
 |
 |
 |
 |
2013年 3月 23日掲載
| 館内の桜が、一斉に開花し始めました、例年に比べ、一週間程度早い開花です。 | |
 |
 |
| 桜 (ソメイヨシノ) | 桜 (ソメイヨシノ) |
 |
 |
| 桜 (ソメイヨシノ) | 菜の花 (ナノハナ) |
 |
 |
| 蒲公英 (タンポポ) | 馬酔木 (アシビ) |